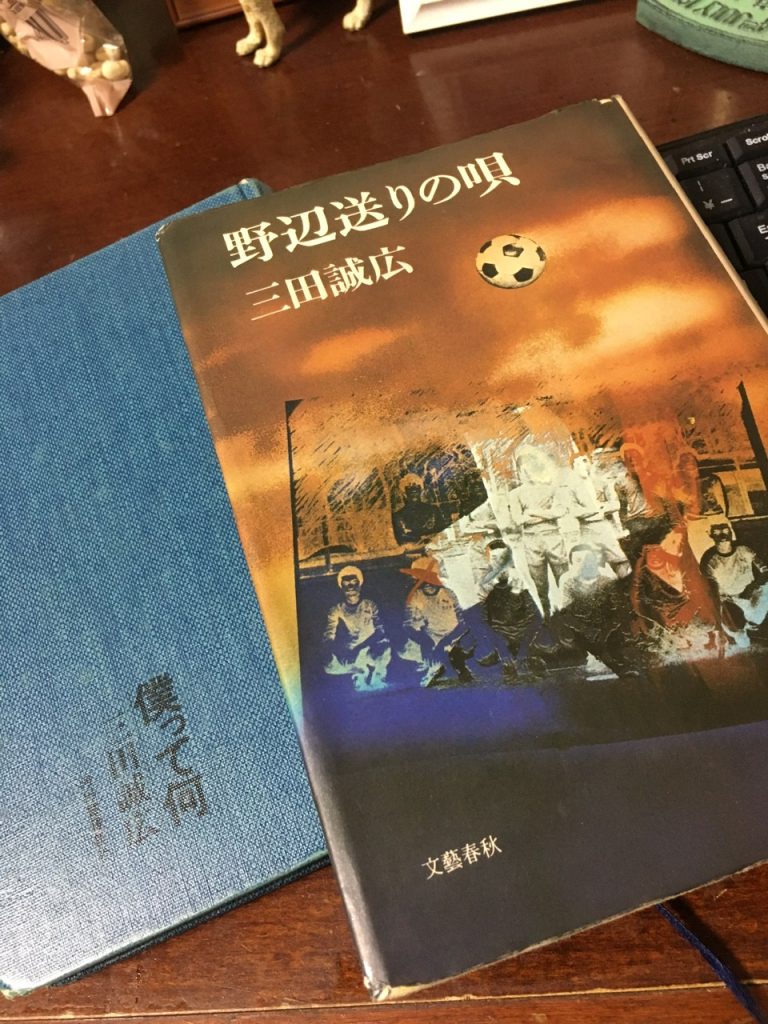今読む「僕って何」「野辺送りの唄」(三田誠広)
三田誠広「野辺送りの唄」を読んだ。
ずっと読みたいと思っていた。実はストーリーも物語のトーンもすっかり忘れ果ててしまっているが、40年前の発刊直後に私はすでに一度読んでいる。そのとき私は衝撃的な深い感銘を受けている。すっかりファンとなり、他の小説も読みあさり、その名が目次にあれば文芸誌や週刊誌を買い求めたのを覚えている。ドストエフスキー作品への傾倒を記した文章やスリランカの日常を綴ったエッセイなど興味深く読んだ。
それは学生時代のことだ。しかし、やがて大学を卒業すると、仕事だの家庭だの怒涛の現実に追われ小説への興味そのものを私はなくしてしまった。当時読んでいたのはユングやサリバンそして仕事に関連する実務的な専門書であり、また吉本隆明など思想評論の類であった。たまに書店で背表紙に三田誠広という名前を見かけることもあったが、いかにも軽妙なファミリー向けのタイトル本であったためもう惹かれることはなかった。だからいつのまにか私にとって三田誠広という作家は、「たしかに一時期その作品群に熱中したものの、それがどういう感銘であったのか実感として思い出せない」という不可解な存在となっていた。芥川賞受賞当時「コピーの三田」で有名な大会社の御曹司だとさかんに報道され、その長髪童顔といった容貌に「僕って何」の頼りなげな表紙イラストが重なり、その印象ばかりが残ってしまっていた。
文芸思潮誌に氏の自伝が連載された。十代から芥川賞受賞に至るまで、作家としての彼の歩みが述懐するように書かれてある。決して自己顕示のいやらしい自己愛的懐古ではない。むしろ淡々と抑え気味に、鬱屈した当時の心情や苦々しい悔いが率直に記されてある。そしてドストエフスキーや埴谷雄高が作家三田誠広の背骨になっていることがよく分かる。当時「僕って何」を読んだ後に「Mの世界」を読んだときの戸惑いを覚えている。彼は連載の中で「僕って何」をリアリズム小説だと述べている。ぴんとこない。それに「野辺送りの唄」だ。どんな小説だったのだろう。私はどうしてあれほどに大きな感銘を受けたのだろう。その引っかかりを解くため、私は図書館に出かけ、「僕って何」「野辺送りの唄」など彼の著作を借りてきたのだ。
1 「僕って何」(1977)を今読む
先に読んだのは「僕って何」だ。発行は77年。この年の芥川賞を取っている。久しぶりに読んだ。田舎から東京の大学に入学したややマザコン風の男子学生が、折からの学生運動の騒乱の中で翻弄されつつ自分という存在にぼんやり向き合う物語である。すぐに気がついた。以前に読んだとき、私の目はまったく節穴だったのだ。そういうことかと疑問は解けた。
これは「野辺送りの唄」よりも前、最初に読んだ三田作品だ。正面から全共闘世代の体験を小説として描いた小説としてき大きな話題となった。しかし当時私は物足りないという読後の感想を抱いた。
京大生山崎氏が死亡した羽田闘争は小6のとき、そして東大安田講堂攻防戦は私が中2のときの事件である。だから全国の大学、さらに地方都市の高校にまで燎原の如く爆発的に拡大し勃発した反体制闘争の盛り上がりを私は直に体験してはいない。その後運動は先細りとなり急進化した。高2の冬、連合赤軍によるあさま山荘事件、続けて日本赤軍PFLPによるテルアビブ空港での乱射事件が起こった。その食堂でよく食事をしていた鹿児島大学でも内ゲバ事件が勃発しており、対立党派が大学に侵入したと学内放送で緊急動員をかけるのを耳にしたりしていた。もう大衆的実力闘争の時代は遠い過去の出来事でしかなかった。しかし例えば高校の文芸部で「されど我らが日々」は当たり前の必読書であったし、「青春の墓標」「二十歳の原点」といったものは当然に読まれている本であった。しかし「されどー」にしてもそれは私が生まれた1955年の六全協時代の物語だった。その空気感に「現在」であった70年代前半とのリアルな連続性を感じることは難しかった。だから、まもなくやがては60年後半の闘争を舞台とした、それこそ新しい「されど」に代わる小説が必ず生まれるだろうと期待していた。しかし、以後しばらく小説はおろか手記さえ、広く話題を呼ぶ作品は出なかったように思う。それはあまりに挫折の痛手が大きくその体験を自身が相対化することも難しく、ましてそれを文学として昇華するには相応の時間が必要だったのだと思う。「されどー」の発表もその時代から9年後に書かれたものことであることを当時の私は知らなかった。
だから「僕って何」を勢い込んで購入した記憶がある。私は大学1年であった。そして読んだ感想は、なんとも肩透かしのような物足りなさであった。闘争に身を投じた青年の激烈な葛藤やその現場で出会った女性との鮮烈な交歓など妄想し期待していたのだ。しかし描かれていたのはそんな勇ましく都合の良い話ではなかった。頼りない学生のみっともない右往左往話だったのだ。
今回その物語を手にし、すぐに自分の読み方の浅さを恥ずかしく思った。実は、すっかり作家の術中にはまっていたのだ。
自分で創作をたどたどしく初めてみると、今さら当たり前のことにぶつかり難渋することも多い。たとえば或る粗雑な、考えることの得意でない男を主人公として、一人称の物語とする。これがまるっきり書けないのである。なぜか。自己洞察に無縁な男であれば、自分の抱いている感情や思考を自ら自覚することなどない。つまり主人公が自分の思いを記述しない小説となるからだ。当たり前だ。「私は自己洞察しない人間であるから、そのとき平気な風を装いながら内心わずかに恐怖を抱いたことに気づいていなかったのである」おかしい。こんなのありえない。きちんと自己洞察できてないとこんなこと言えないだろ、となる。「私は愚鈍であるから、即座にその意味を理解しながらも言い返すことができなかった」愚鈍なんてそれ謙遜だろ。そう分かってるなら愚鈍じゃない。つまり一人称小説は、その主人公が見て感じた風に語り、叙述するのだ。繊細な主人公であれば、その語りもわずかな機微を逃さぬ繊細なものとなる。内向的な人物像ならおのずと内面に焦点を当てた語りとなるし、勇猛な人物であればその語りも力を感じさせるはずだ。それが一人称小説だ。台詞以外の叙述も、主人公の心の声であるからその人格像を大いに表現するのである。
「僕って何」の主人公は、成り行きのまま党派の活動に関わり、切迫した現実について理解を深めたり自分の選択の必然を問うこともなく、ただあたふたするばかりだ。だから、叙述もただ流されるままあたふたしている本人が見て感じたままの言葉であって、状況に流されるまま右往左往している自分を客観的な目で描写するなどありえないのだ。そのためさらに主人公の浅はかな頼りなさが読者に染み入り、なんとも歯がゆい思いにさせられるのだ。これは、たとえばあらゆる面で人に劣る無能な人物として配役を演じるのならば、俳優が演技者として優れていればいるほど人よりも劣るように見え、演出者の指導に従順で律義に応えるまじめな俳優こそがだらしない無法者を演じあげることができるのと同じだ。
「僕って何」は叙述全体が中身スカスカで頼りない。それは作家が中身スカスカということでは決してない。当たり前のことだ。むしろ物語を紡ぐ作家としての力量による技なのである。しっかりと「僕」という浅はかで頼りなく、それでいて悪意の無い小市民的善良さを持ち合わせた青年像を完璧に創造しているのである。「僕」に共感するにせよ、反感を抱くにせよ、それは作家の意図による勝利ということになるのではないか。
学生運動をこのように見るべきだ。あるいは、巻き込まれた青年たちの心情を代弁するとか、そういうさもしい啓蒙的な意図はないと思う。だから作家自身が語るように、これは立派なリアリズム作品なのである。
こうした創作にまつわる作家に対する誤解はつきもののように思う。これは先にも述べた、演者と配役を重ね合わせてしまう錯誤と似ている。
実は私は舘ひろしという俳優がどうしても嫌いだった。コミカルな役を演じてもダンディーな初老ぶりを強調されても、舘ひろしは「嫌な奴だ」という彼が若い頃から印象はずっと変わらなかった。どうしてその印象が私に形成されたのだろう。還暦を前にして、私はようやくはたと気がついた。なんのことはない。学生時代に見た、映画「野生の証明」のせいであった。映画の中で彼は、地方政財界を牛耳る悪徳右翼実力者(三国連太郎)に溺愛される一人息子で、ネオナチ風暴走族愚連隊のリーダーであった。父の悪行を暴こうとする正義の美人ジャーナリスト(中野良子)を強姦して殺害するなどやりたい放題。最後は正義の健さんを殺そうとして逆に殺害されてしまう典型的なヒールであった。私は映画を見ながら、舘ひろし(もう配役名も覚えていない)にたまらない反感を抱いたのを生々しく思い出した。これが原因だ。はっきりと合点がいった。そして強固な印象形成がこのように作られるのだとそら恐ろしい思いがした。なんとも愚かな話だが俳優の演技に限らない。だから、あのように冷めた目をしているにも拘わらず、先に触れた出自や容貌から作家自身と「僕って何」の「僕」とどこかで印象をつなげているところがあったのではないか。軽妙でいくぶんユーモラスでもあるその代表作のために、もともと作家の本領である繊細な精神性が受け止められていない。作家の名を広く知らしめた作品であるから作家活動を大いに推進させもしただろうが、ずいぶんその誤解に煩わされたのではないだろうか。残念である。
ともあれ学生時代には気づくことのなかった、軽妙な作品を生み出す作家の凄みを今回よく理解することができた。
ところで小説の冒頭で「電気釜」という言葉が出てくる。電気炊飯器のことだ。何百年も使用されてきた鉄釜に代わって社会に登場して「電気釜」。最近あまり耳にしないので、若い人たちの中には「電気釜」と言われてもわからないかもしれない。また「部屋の中の『ステレオ』」という記述もある。もはやステレオコンポ自体彼らは見たこともないだろう。そもそも「オルグ」も「セクト」も聞いたことなければ、その説明を聞いて語意を理解したとしてもそれを日常会話で使用していた感覚は実感できないだろう。数年前、京大の人文系大学院を優秀な成績で卒業したという新入社員が「中核」のことをまったく知らずとても驚いたという話を聞いたが、もはや驚くべきことでもなくなっているのではないか。その時代の価値観や空気感が理解されないのは仕方のないことだが、単語やそれが指し示すもの自体が時代の流れの中で具体的に姿を消してしまうことも多い。小説にそういう単語が頻出すると、いかにも古臭く読む気を萎えさせてしまう。とはいえ、たとえ50年100年前の小説であってもきちんと現在に通用する物語もあるし、そもそも外国の小説であれば知らないものづくしである。むずかしい。「僕って何」はアイコンに頼った小説の書き方とはなっていないから、物語の意図は伝わってほしいが、どうだろう。なにしろ50年前が舞台だ。私が高校生のとき半世紀前と言えば大正時代となる。一定の知識教養がなければちんぷんかんぷんだろう。若い人は「僕って何」を読み、どう思うのだろう。今は見ることのできない事物や情景を、彼らはどのように彼らなりの理解をするのだろう。
あえて口に出さずとも来世を信じていた時代の死や生のとらえ方が、今では理解がむずかしいように、今当たり前に備えているものよりも、失ったものの方が私たちに深い示唆を与えるのかもしれない。ならば共有されないことを怖れるよりも、むしろ差異を生じさせることこそが小説の肝のようにも思えるのである。
2 「野辺送りの唄」(1981)を今読む
「僕って何」に続いて、「Мの世界」「赤ん坊の生まれない日」を読んだ記憶があるが、前者には戸惑いを覚えるだけで読み切ってはいない。後者については抱いた感想すら覚えていない。そして「野辺送りの歌」を読んだのだ。その感動と衝撃は先に書いたとおりだ。
今回、図書館書庫から取り出してもらったその単行本の装丁にははっきりと見覚えがあった。私は四十年ぶりにその頁を開いた。
こんな小説だったのか。
ストーリーにまったく覚えがない。初めて読むように、私は物語を追った。
落ち着いた繊細な文体だ。「僕って何」の文体とはまったく異なる。むしろ「僕って何」では、あえて自意識の浅い幼稚な思考をそのまま一人称の語りとして描写していることがよくわかる。こちらの主人公文彦は自分の心の動きに自覚的である分、内心のささいな汚濁にも気をとられてしまう。ときに嫌悪を抱き自分を苛み、それでも健康な人のように振る舞っている。その描写はとてもリアルだ。自分の心の動きをリアルタイムで自覚してしまう過敏さをよく知る人でなければ書けない。きっとこちらの方が作家にとってはすんなりと入って行ける心的世界なのだろう。
しかし主人公はそのように繊細でありながら、高校時代サッカーの花形選手であり、女生徒たちからの憧れに対しては覚めた態度で無視している。これは女性をうっとりとさせるむしろベタな外的振る舞いだ。自覚以上にモテる人物なのだ。これが、もしうじうじとした孤独な心のままたとえば文学に逃げ込んでいるキャラクターであれば、物語は一気に暗く閉じてしまっただろう。だから作家は、そうした単独者の孤独な心理を抱えたまま社会に溶け込み、能力を発揮できる人格像を措定したのだろう。孤独な寂寥を抱えつつも、なんとか社会と折り合おうともがいている者にその人格像は憧れであり、救いだ。そして私もそこに惹かれたのではなかったか。
舞台の大学は学生運動の真っ只中である。大衆団交に重なって政治党派同士の熾烈な憎悪と暴力が爆発する。その時代の空気を吸ってはいないが、その描写によって生々しく想像することができる。
罵声と怒号による喧騒渦巻く大衆団交という閉じた空間。それはそのとき参加した者が特権的に目撃した貴重な体験である。もはや類似の体験すら困難となっているからだ。貧相な想像力と無知で歪曲し、権威と多数にすがりつく者たちのテロリスト呼ばわりなど滑稽の極みだが、その時代を生きた人々であってももう思い出したくはないと否定する人も少なくないかもしれない。しかしそうした異常な事態の体験は、少なくとも作家にとっては宝ではないか。それは日常こそが教師であるのと同様に、そうした究極的な現実状況こそが世界や人間の無辺際を窺い知るリアルな契機となるからだ。体験をそのままに書くことがなくても、それは必ず創作の滋養となるはずだし、またそのように昇華するのが作家ということになるのではないだろうか。
怒号と罵声飛び交う喧騒しかり、人間が物理的に激しくぶつかり合い合い、たくさんの呻きや喚き声が重なり合って響く尋常でない逆上と興奮の坩堝であるとか、現代でそれを想像してもやはり小集団が想定されてしまうのではないか。だからやはり60年代末に出現したのは、まさに群衆の武闘だったのだと思う。
そうした激昂する群衆の熱気のただ中で、冷めた孤独な主人公が苦しむのは、嫉妬であり屈辱だ。かつて親友であった者への憎悪と愛執する女性に捨てられた惨めさ。政治党派で熱心に活動する二人の誠実を傍観しながら、主人公は反感と自虐を振り子のように反復するしかないのである。
そして、事件が起こる。
不意に起こる。想像もしなかったことが、突然起こる。その描写も本当に見事だ。抑えた筆致が読者を引きずり込む。まるでそこに立ち会ったかのように、事態を受け止められず理解ができず、呆然としたまま、じわじわと底知れぬ戦慄が心の底から静かに染み込んでくる。
その恐怖は暴力や死そのものに対するものというよりも、問答無用に突然容赦なく振り下ろされる冷酷な定めの前に、人はいかに卑小で無力な存在かと徹底的に思い知らされる、そういった戦慄なのである。
ここでは深入りされていないが、こうした凶事に対し復讐を以て遺志に報いるという態度を、個人の死を政治利用する党派の姿として描かれている。政治党派の非人間的な卑劣さが描かれていると見ることもできるが、被害者を前にしたならば加害者へ怒りをたぎらせ、決して容赦することなく復讐するというひとつの人間的態度を政治組織に仮託して描いているようにも見える。小説の中では、政治党派のメンバー以外、肉親親族すら誰一人、加害者=敵に「怒り」を抱く者はいない。これは三田小説のひそかな鍵ではないか。通常、難事に出会えば○○のせいと無理やりにでも犯人を措定して自分の免罪を図るのが人間の常だ。さらに最近では、犯人を許すことは、善悪の観念に欠け、道徳心が乏しいのだと非難される傾向すらある。そのまなざしから見れば、怒りを表わす者がいないというこの物語は異様である。抗しがたい災害に遇ってしまったかのような、一種の諦念が見える。そしてこれが私には三田小説に漂う、ものがなしい透明な静謐さの核心のように思う。主人公の怒りを阻んだのは、彼自身の罪意識ではないか。
そして物語はここからが悲しい。
大学を卒業し、メーカー企業の社員となった主人公は、一度は自分を捨てたその女性と結婚する。かつて親友の死に際し「親友を殺したのは自分だ」とまで自分を苛みながら、一方で彼はひそかにその死を喜び勝利者としてほくそ笑んだ。その深く引き裂かれた傷跡のような刻印は、時間がたっても彼を苦しめ続ける。夫婦でありながら二人の間には精神的にも肉体的にも暖かいつながりは体験されない。沈痛である。こころの「先生」は自死するが、主人公はサラリーマンとして苦労を経験しつつも順調に出世してゆく。そして動乱の学生時代をとこに過ごした者たちそれぞれの人生模様も交差する。
繰り返すがこれは主人公の一人称小説である。描かれるのは、主人公が見た世界だ。彼は妻がどう思っているのか、疑念を募らせ、苛立ち、そして沈みこむ。亡くなった恋人を今でもわすれずに思っているのか。夫である自分を愛しているのか。憔悴が常に彼の深層を蝕んでいる。痛ましい。しかし、実際のところ、彼女が見ていた世界はまったく違ったかもしれない。
会社社会においては無難に振る舞えても、目の前の人に正面から裸で向き合い、自分を開くことのできない自意識の塊のような夫。いつまでも遥かな過去にこだわり嫉妬深いだけで、女のむきだしの生理を感受し受け入れ、自分を投げ出すことができない下手くそで無神経な男。それでも他の女に現を抜かすことなどありえないし、酒もばくちもやらず、十分な経済を保証してくれる。そしてなにより、どんなに稚拙なやり方であっても、心底私に惚れ込み大事にしようと痛ましいほど努めている。待てばよい。夫が大人になり、ようやく物事がわかるまで、待てばよい。その日は来ないかもしれないが、私はそれでも待つ。
そう思っていたかもしれない。あるいは、妻自身が軽い精神疾患に長く陥っていたと見ることさえできる。
これは「英雄の物語」だと独特な言いまわしで作者は評している。勝手な私の印象ならば、これは紛れもない「回復の物語」である。その深刻な痛手は、原因の除去であるとか、心理療法的アプローチによってではなく、つまりロゴスの力によってではなく、耐え抱えてただ歩む末に、これも不意にもたらされる賜物によって実はすでに回復していたことが知らされるのである。
私がかすかに断片として覚えていた小説の一節は、性的行為によって妻が声を上げるのを楽器と聞く場面だ。これが唄なのである。葬送のための「野辺送りの唄」。その回復、もたらされた救済に、読者である私も救済され深い安堵を覚えたのである。
「僕」もそうであったが「文彦」も人のせいにすることができず、まさに生きづらさをひた隠しにしながら、人を責めず、むしろそれを自分の弱さとなじりながら黙々と歩むのである。人からの認証や承認を糧とはしても決して武器とはしない断念の気配には、ひたすら内を見つめつつ質素に生きる聖の気配すら私はうっすらと感じ取るのである。
素晴らしい小説だ。
若い時分に感動した作品を年老いてから見返して、ひどく赤面することもある。こんなものに感動していたのかと自分が腹立たしくなる。しかし「野辺送りの唄」は40年たった今読んでも、深い感銘に打たれた。
「野辺送りの唄」は文庫化されていない。県立図書館で所蔵の1982年から現在までの貸出票を見ると30回しか貸し出されていない。それが社会的な評価なのだろう。しかし、私の感動は他人や社会の評価などまったく関係なしに揺るがない真実だ。惜しい。実に惜しい。
私がここまで作品に打たれるのは、その主題とトーンが、私にとって個人的に響き共鳴するからだろう。些末なことだが、高校時代留年しているだけでも私は勝手に近しさを感じる。この小説の主題は、私に言わせるなら、死と生であり、罪だ。あくまで私の読み方に過ぎないが、三田誠広自身がドストエフスキーに傾倒し、後年宗教を題材としたたくさんの書物を著していることもすっかり合点がいくのである。
冒頭、私にとって三田誠広は不可解で奇妙な存在だったと書いた。40年ぶりに著作を読み、明解となった。尊敬する作家である。深遠で重厚なテーマの長編群を私は読んでいない。ドストエフスキーの新訳や、続編も楽しみだ。巨大な鉱脈を当てた気分だ。しかし読み果たすのに時間はかかりそうだ。長生きせねばなるまい。これが、40年ぶりに三田誠広を今読んだ感想である。