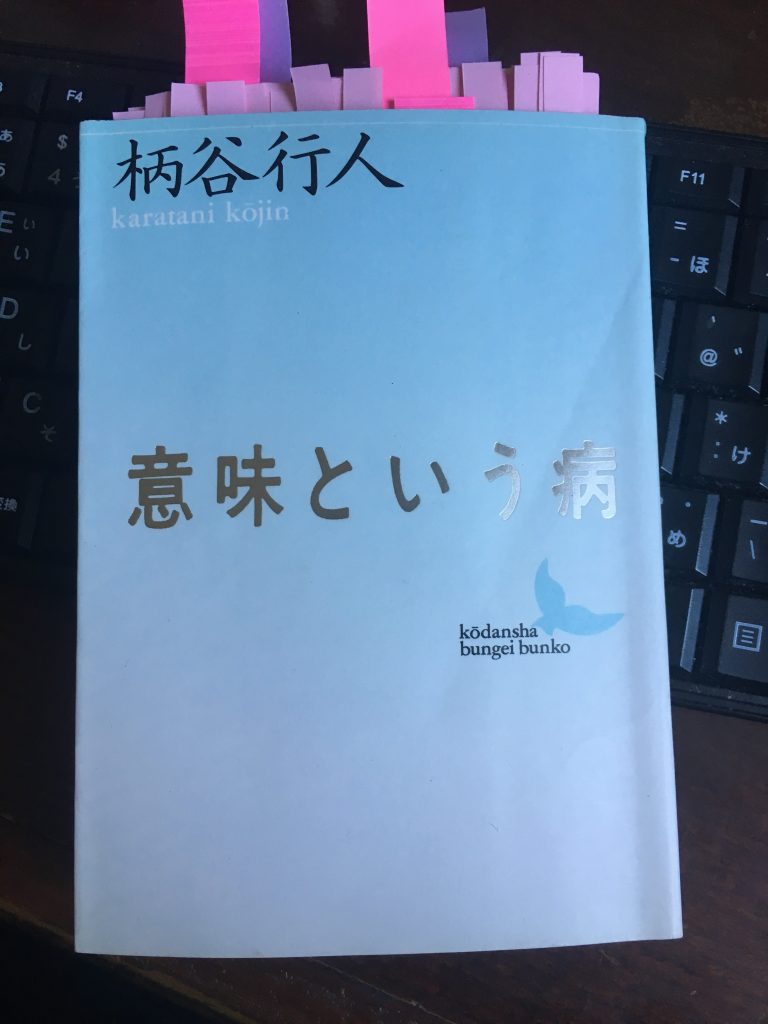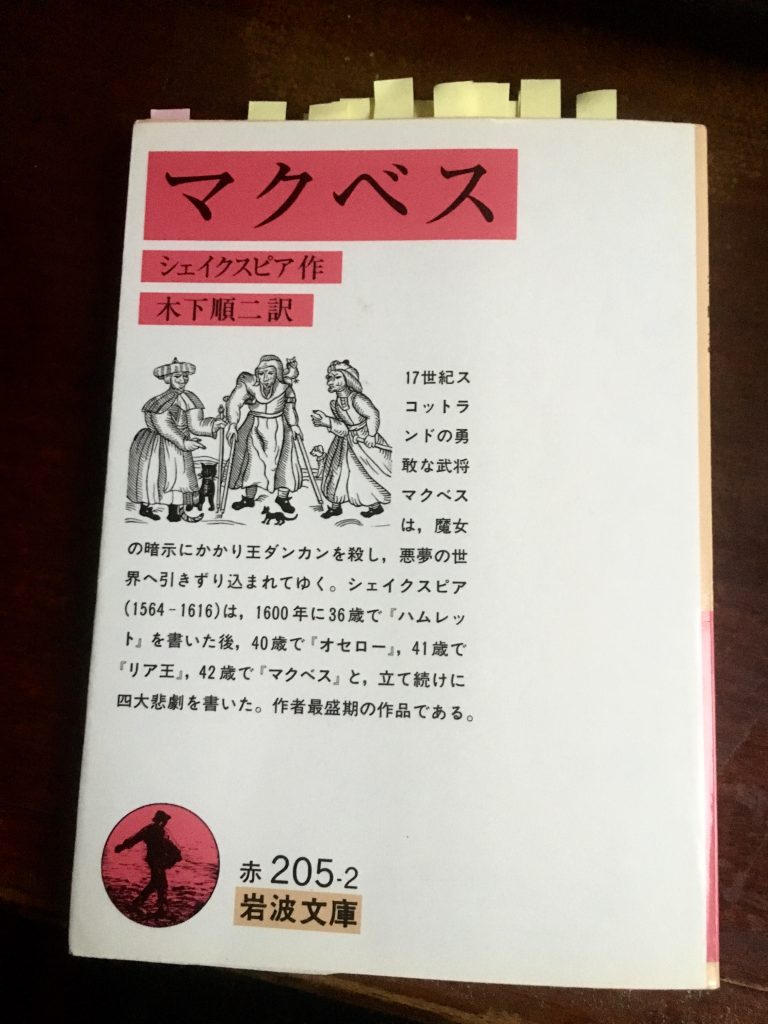柄谷行人「意味という病」1975
他のシェイクスピア悲劇の戯曲と同様、「マクベス」の読後にも不可思議な評価不能の無音状態に心が停止した。
これまでどおり発酵するまで少し時間を置いたらよかったのだが、古書店の店先で開いた文庫本の冒頭にこんな一節を見つけてしまった。
「『ハムレット』の中に、『芝居の目指すところは、昔も今も自然に対して、いわば鏡を向けて、正しいものは正しい姿に、愚かなものは愚かな形のままに映しだして、生きた時代の本質をありのままに示すことだ』という有名な台詞がある。これはシェークスピア自身の芸術論と目されているが、むろん今日のリアリズムというような文芸思潮とは何の関係もない。だが、これを心を虚しくして自然を視ることだといって澄ましていていいわけではない。この素朴ないい方の中には、おそらくドストエフスキーのような作家だけが匹敵しうるような凄まじい明視力がひそんでいるからである。」
迷わずまっすぐに店のレジに向かったのは言うまでもない。柄谷行人の「意味という病」講談社文芸文庫である。
引用は「マクベス論 ーーー意味に憑かれた人間」
引き込まれ目を見張りながら読破した。凄い。シェイクスピアとそしてマクベスに抱いた無音の飽和のような曖昧模糊が次々に隈取られ形と色が与えられてゆく。そして隙の無い硬質な文章が打ち込むように颯爽として酔わされる。思わずためいきである。
柄谷行人については可能性の中心とか何度か手に取ったことはあったがあまりに難解で到底読み進めることができなかった。読了できたのは「政治と思想1960-2011」だけだが、これはインタビューなので柄谷の著書とは少し言い難い。はなから私には敷居が高すぎるとこれまで敬遠していた。だから期待せずに手に取った一冊ですっかり印象が変わるのだからわからない。また、だから読書は面白いのだ。筋書きはない。
濃密である。柄谷のマクベス論について書こうと思っても、全部読んでください、と一言で済ませた方がよいようにも思われる。それでもいくつか二回通読した時点での感想を記しておきたい。
まず、シェイクスピア劇が時代の知、つまり当該時代で当たり前に常識で「普通」とされている価値観から自由に超えているという点について柄谷はするどく触れている。これはまず私たちが発想する精神の営みはまったく根底的に時代に制約され支配されているという冷徹な現実認識が先にある。これは私たちの価値観が普遍性を有しない相対的なものにすぎないということにとどまらず、「自分の思い」「自分の考え」と感じ思っているものが実は錯覚に過ぎず「そう思わされている」「そう感じさせられている」のであって、実はそこに「自分」は存在していないのである。操られているパペットに過ぎないのに大真面目に私たちは架空の自分を想い語り生きているのである。この或る意味絶望的な宣告を我が身に思い知っていなければ、シェイクスピア劇が時代の制約を跳躍していることのすさまじい奇跡に圧倒されることもない。
実は限定は「時代」という「時」だけにもちろんとどまらない。場にしてもそうである。地域、町、地方そして「国」にも決定的に規定されており、ここで自ずから血がからみ「民族」という奇怪な呪縛に生まれながらとり憑かれ、取り込まれ、洗脳されているのである。なにごとか自身のアイデンティティを民族国家に同一視する生来の病を自覚する者とその病の渦中にあって誇らしく自覚しない者との熾烈な差異は和解が不能にすら思える。そしてこれら、時と地域と血を超越していることが「古典」の必要条件となるのだが、現在もてはやされているその理由が現在の時と地域と血が影響していることもあり、その審査は困難である。これらのことを言い当てているのが、冒頭に引用した「ハムレット」の一節である。
「正しいものは正しい姿に、愚かなものは愚かな形のままに映しだす」
シェイクスピアは、時代や国家や民族という制約に無自覚なまま支配された「正しさ」を退いた場所から俯瞰してから近接して描いているのである。だから、シェイクスピアには「何が正しく、何が愚かであるか」という価値尺度が「ない」のである。なぜなら、正しさなど価値尺度が、上に見てきたように実はそもそも錯覚幻想にすぎず「ない」からである。
ここまで書くとアナーキーなニヒリズムに陥っているように誤解されかねないが、逆である。一切に対するその尊厳への畏敬の道なのである。だから正しさを振りかざし、或いは無様に愚かな姿をさらす、それらあらゆる人の営みに対する無言の圧倒的な慈しみがそれこそシェイクスピア劇にあふれていることが見えるではないか。
そしてこれを「書く側」から述べるならば、まずその途方もなさ、無力感に襲われるのはやむえないことと思われる。
何よりも作家自身が足の指先から頭のてっぺんまで、時代と地域と血に支配されており、その眼差しでしか書くことができないからだ。これは何も私が描く人物が思い語り行う内容のことではない。また例えば群像小説であれ、登場する人物出来事事態を俯瞰して描く隠れた作家自身が否応なく支配されているということだ。
ここで作家がその桎梏を逃れる方法の一つとして現れるのは、むしろこの桎梏を自覚しないまま支配され生きている人物になりきって描くことで、逆に読み手に桎梏の有り様を伝える手法だ。これをそのままリアルタイムな主観世界の錯綜交錯を変遷する事態に組み上げたのがドストエフスキー小説群に思われる。それはともかく、自身の偏狭をなんとか少しでも逃れて、時代地域血から自由な境涯からの書き手への接近を切望するのである。これが、私が「魂の文学」を渇望する所以である。
また、柄谷のマクベス論から浮かび上がる、犯罪における精神の喪失というか、強いられた意志による行動についてだ。絶対に自分はそんなことなどするはずがない、と固く確信しながらも行為にいたる人間の心理、有り様についてである。これもどれだけ検討や議論を深めても足りない公案に思われるし、そこに「予言」とは何か、という恐ろしい問いがある。先に見たように、「自由意志」なるものが錯覚や幻想であるならば、「未来」は誰のものであるのか。つまり、私の未来は誰が決めているのか、ということである。
今回はここまでにしておきたい。さらに、深めてゆきたいことは言うまでもない。この論集には「マクベス論」以外にも刺激的な論文が多数収められている。