沈既済「枕中記」(AD8?);世阿弥「邯鄲」(AD14?);芥川龍之介「黄梁夢」(AD20)
● 沈既済「枕中記」
中国故事に言う「邯鄲(かんたん)の夢」の元になった物語と知らずに読んだ。だから最後の種明かしにすっかり驚いた。「邯鄲の夢」とはいわゆる「夢オチ」のことである。しかし、知らずに読めば「枕中記」物語に「夢オチ」を予感させる展開は一切ない。物語はこう始まる。
うだつのあがらぬ自分の人生を青年は道士に嘆く。やがて眠気を催し道士の勧める枕で横になる。寝入りばな、不思議なことに枕の穴に自分が歩み行き、そして家に帰る。やがて数か月が経過する。そして主人公盧生の波乱万丈の人生が始まる。美女を妻と迎え、官吏試験に合格し、めきめき能力を発揮し、重用される。出世を重ねながらその才が王の目に留まり、抜擢されては派遣先で見事に功をおさめ応える。官位を一つずつ駆け登るが、嫉妬を浴び、讒言で官位を引きずり降ろされる。それでも懸命に努め、またさらに高位へと出世するが、また妬みに遭い、無実の罪で投獄される。一度は絶望し自死をはかるが、妻の懇願もあって死を免れる。晴れて冤罪が明かされ宰相にまで登り詰め、善政で人々から愛される。やがて年老いて、孫も十人を数えようやく平穏な老境を得る。一儒士に過ぎなかった自分が送った栄華と波乱の人生を振り返り、感謝を胸に八十年の生涯を閉じる。と同時に目が覚める。夢であったのだ。五十年にわたる人生を生きて死んだが、それは覚めてみればほんのひと眠りの間の夢だったのだ。放心状態で「夢だったのか」とつぶやく青年に道士は言う。「人生もまたそういうことだ」と。青年は道士に感謝して「寵辱の道、窮達の運、得喪の理、死生の情、よくわかりました」と述べるのである。
これは凄い。まず時間の流れがすっかり変わっていることだ。寝ていたのはほんの数十分だったかもしれない。しかしその間に夢の中で、ごく普通に五十年の時間を体験しているのだ。普通に朝起きて、働き人と会い語り、また食べ、夜には寝ていたのだ、夢の中で。それは夢の中であれまさにリアルな生活体験、人生体験である。だからなのだ。人生が夢のようだということは、つまり果たしてどちらが夢なのか、と思わせるほどなのである。
凄い物語だ。「なんだ夢だったのか」という程度の話ではない。夢こそ現実と思われ、ならばこの現実こそ夢なのかと思わずにはいられない強烈な体験だ。
それこそ現代日本のドラえもん映画やライトノベルの異世界転生ものまで派生させたそのルーツと言える物語だ。圧倒される。作家は歴史家としても名を馳せた有能な官吏として記録に残っている。八世紀、日本がまだ奈良末から平安初頭時代の人物である。
● 世阿弥「邯鄲」
作者は世阿弥とあるが異説もあるようだ。上記の「枕中記」をもとにした能楽の謡曲である。舞台は中国邯鄲で、主人公の名は盧生。「枕中記」と同じである。しかしその他は随分と変更された脚色だ。
「枕中記」の盧生は闊達な青年で無為平凡な日常に耐え難さを抱き出世による栄達に心底憧れている。飽き足らない衝動を持て余した青年らしい姿が思い浮かぶ。一方、この謡曲「邯鄲」における盧生はその第一声が「憂き世の旅に迷い来て、憂き世の旅に迷い来て、夢路をいつと定めん」である。高僧に道を尋ねんとつらい忍土を漂泊する迷い人の虚無的な嘆息が聴こえてくる。「住み馴れし、国を雲路の後に見て、国を雲路の後に見て、山また山を越え行けば、そことしもなき旅衣、野暮れ山暮れ里暮れて、名にのみ聞きし邯鄲の、里にも早く着きにけり」なんとも孤独で虚無的な疲弊が伝わってくる。そして彼に枕を勧めるのは道士ではなく、宿の女主人である。
そして眠りにつくや男に起こされる。男は皇帝の使いである。なんと皇帝の玉座が譲られるのである。御輿に乗って宮廷に入る。目も眩む夢のように豪華瀟洒な世界である。溢れる宝物、かしづく美女たち、ひれ伏し礼賛する人々の波。そして君も民も豊かに栄え平和な世が続く。そして舞台で舞い、日がな一日歌ううち、春夏秋冬季節が巡る。在位五十年を経て、やがて栄華は消えはて目が覚める。粟飯が炊けたと盧生を女主人が起こしたのだ。美しい女官たちの声は松の木を渡る風の音になった。宮殿楼閣はあばら家の宿。栄華の日々はただ、飯ひと炊きの間の眠りに過ぎなかった。「百年の歓楽も、命終われば夢ぞかし」「げに何事も一睡の夢」と謳われる。
謡曲で盧生が夢で体験するのは、信じられぬほどの栄華歓楽である。そしてまさに夢と消え果てるのを体験し、その虚しさを知るのである。
ここが異なる。「枕中記」では、「寵辱の道、窮達の運、得喪の理、死生の情」といった光と闇、上から下、有頂天と辛酸それら快と苦の両方を体験してこの世の行き道を知る。「邯鄲」では、良きものと人が求めることの虚しさを教えるのである。豪奢を避け質素を、生き方においても尊んでいる。
能楽の観覧者は武士たちである。彼らがその物語を求め、或いは能楽師たちが武士にそれを望んだのかもしれない。下手をするとニヒリズムに転落しそうになりながら、虚しい栄誉栄華でなく人が人生に求めるべきものは何かを尋ねている。
● 芥川龍之介「黄梁夢」
そして芥川の「黄梁夢」。これは千二百字にも満たない掌編である。盧生が目覚めたところから描かれる。道士は盧生に「人生も夢と変わらない。得喪の理も死生の情もつまらないもの」と得意げに語る。ここからが芥川の真骨頂。盧生は目を輝かせ反論する。
「夢だから、なお生きたいのです。あの夢のさめたように、この夢もさめる時が来るでしょう。その時が来るまでの間、私は真に生きたと云えるほど生きたいのです。あなたはそう思いませんか。」
道士は顔をしかめた、と結ぶ。
痛快である。これでようやく千年を経て「枕中記」が完結したような気がする。もう若くはない私は、顔をしかめる側だがそれで良い。青年ならそうでなくっちゃとも思うのだ。
▼沈既済「枕中記」
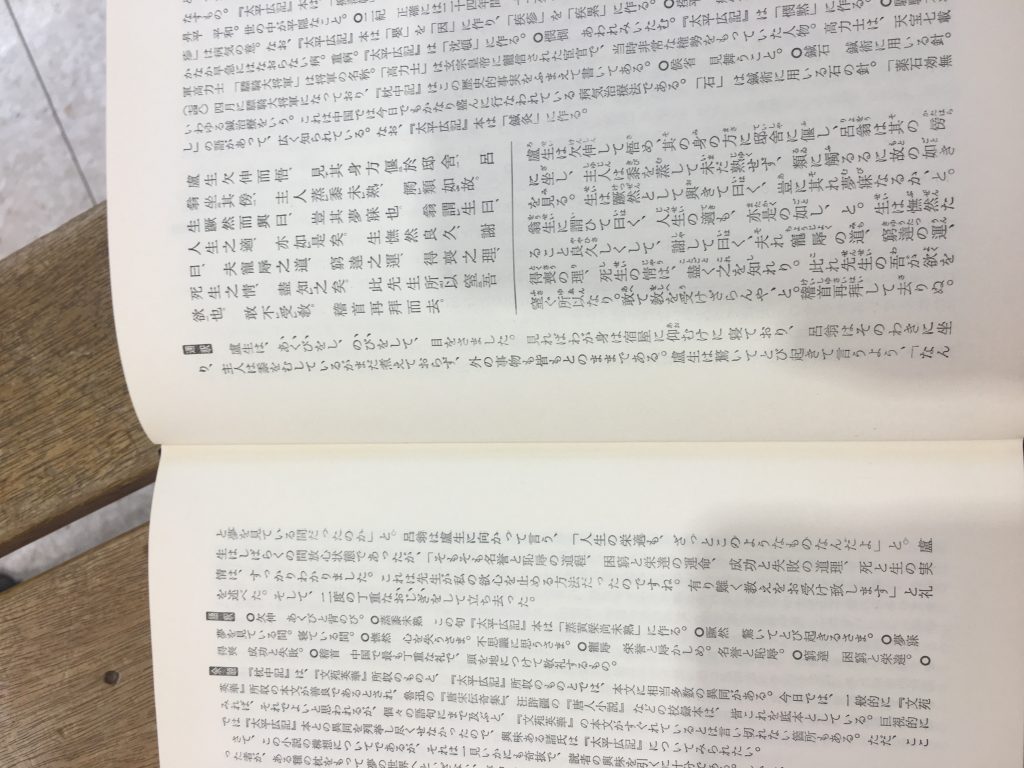
▼ 世阿弥「邯鄲」
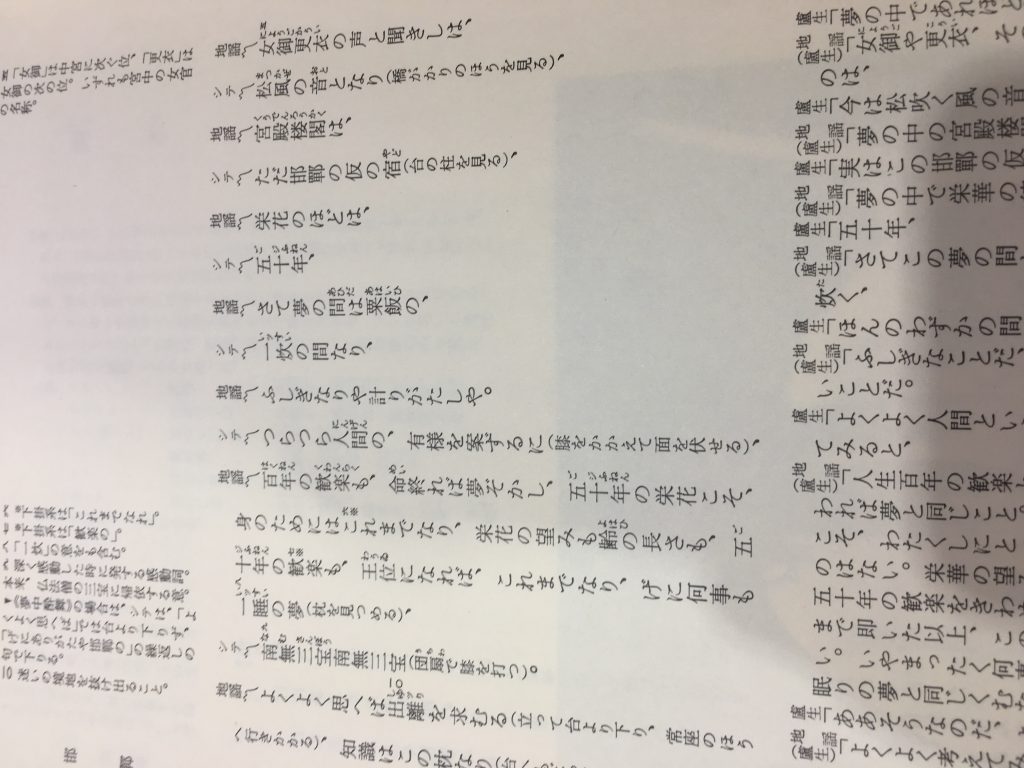
▼芥川龍之介「黄梁夢」
青空文庫リンク

































