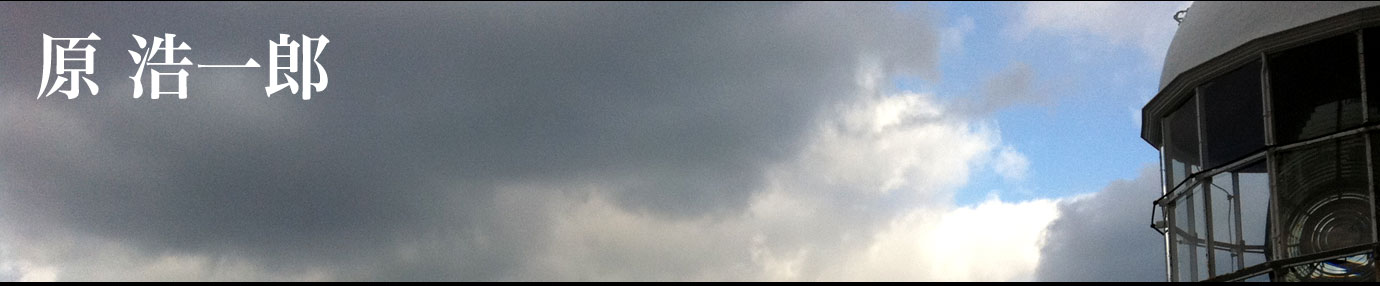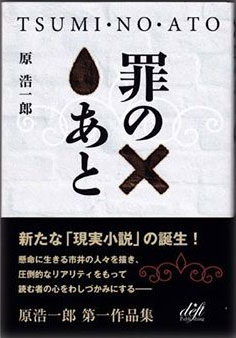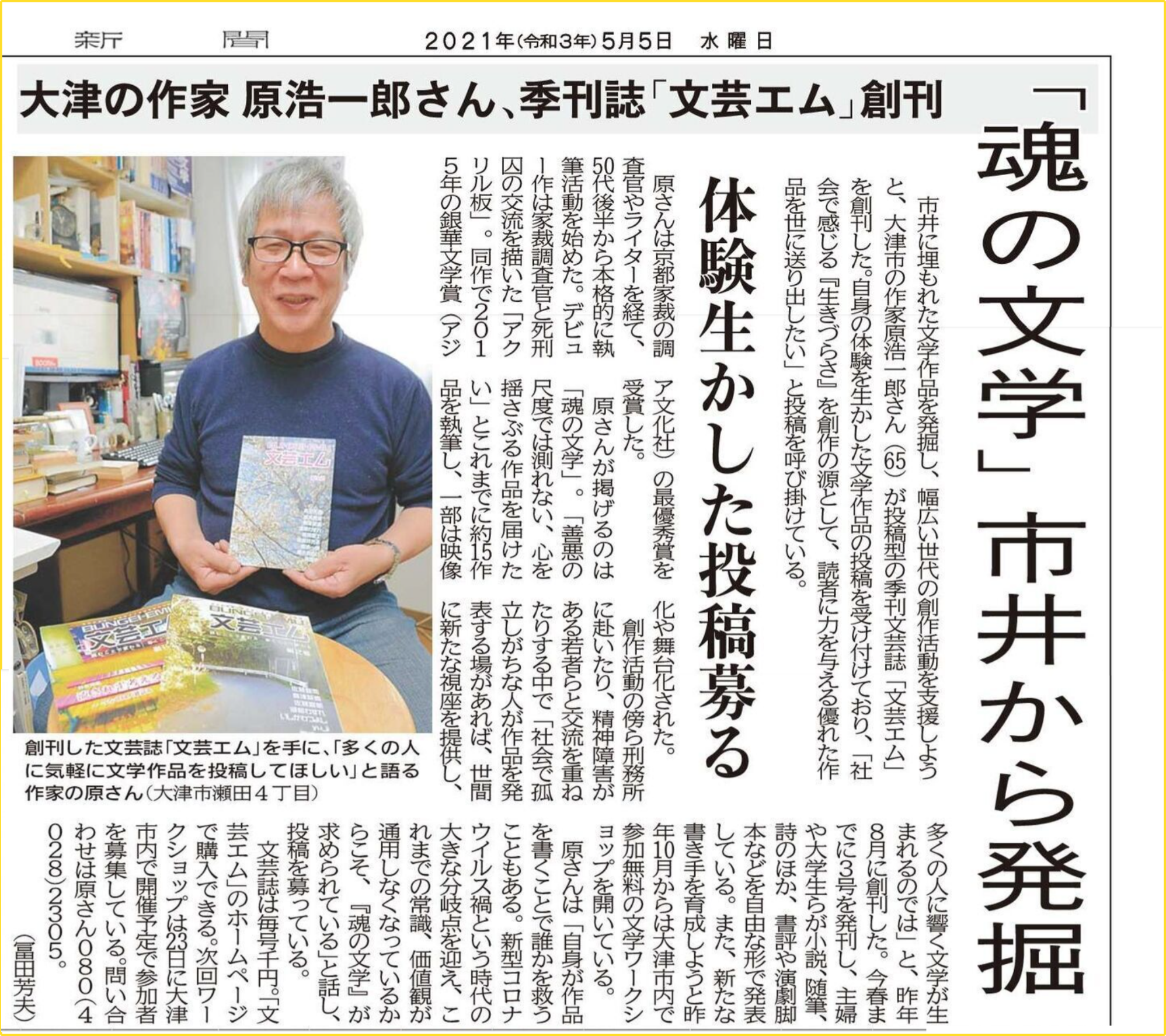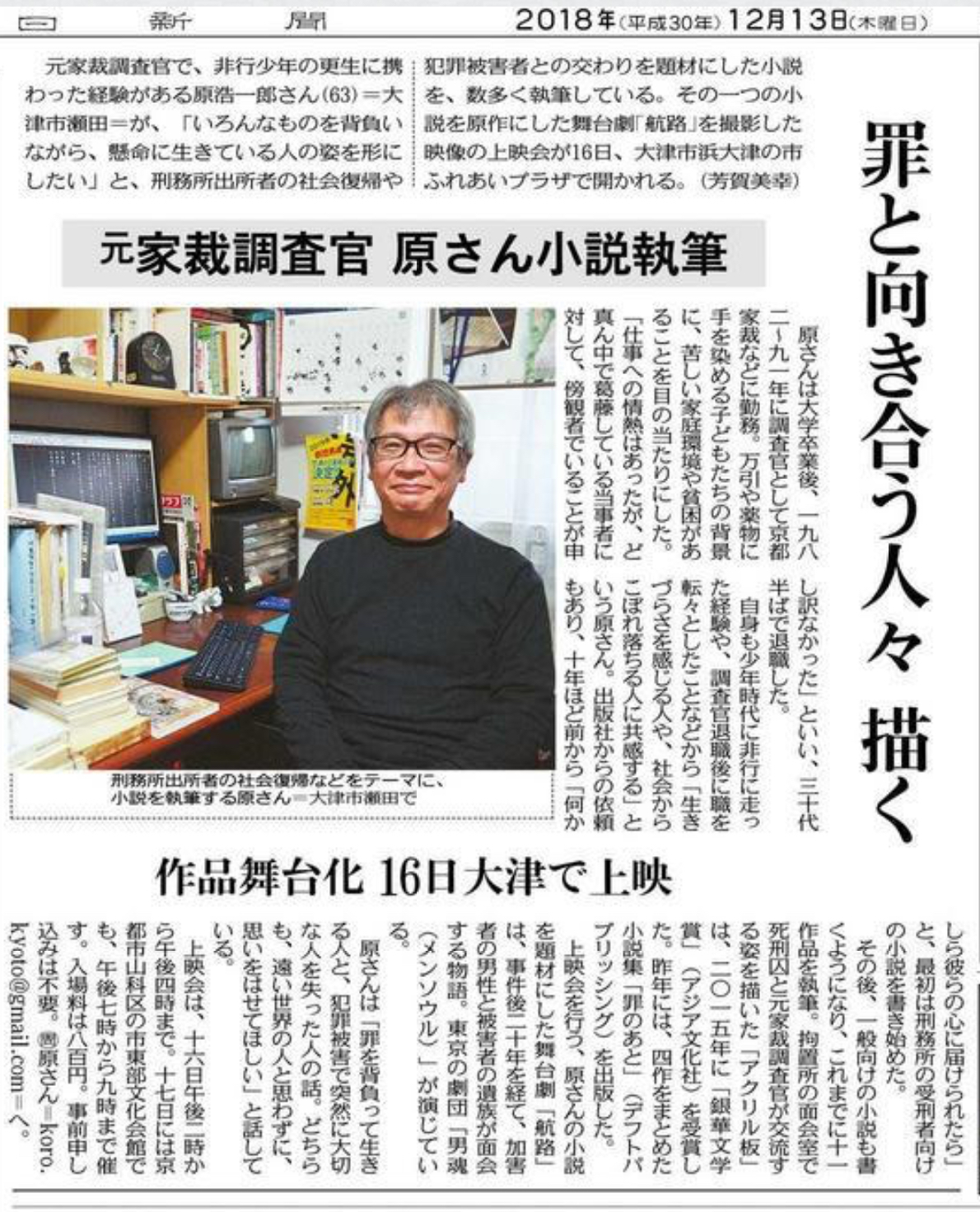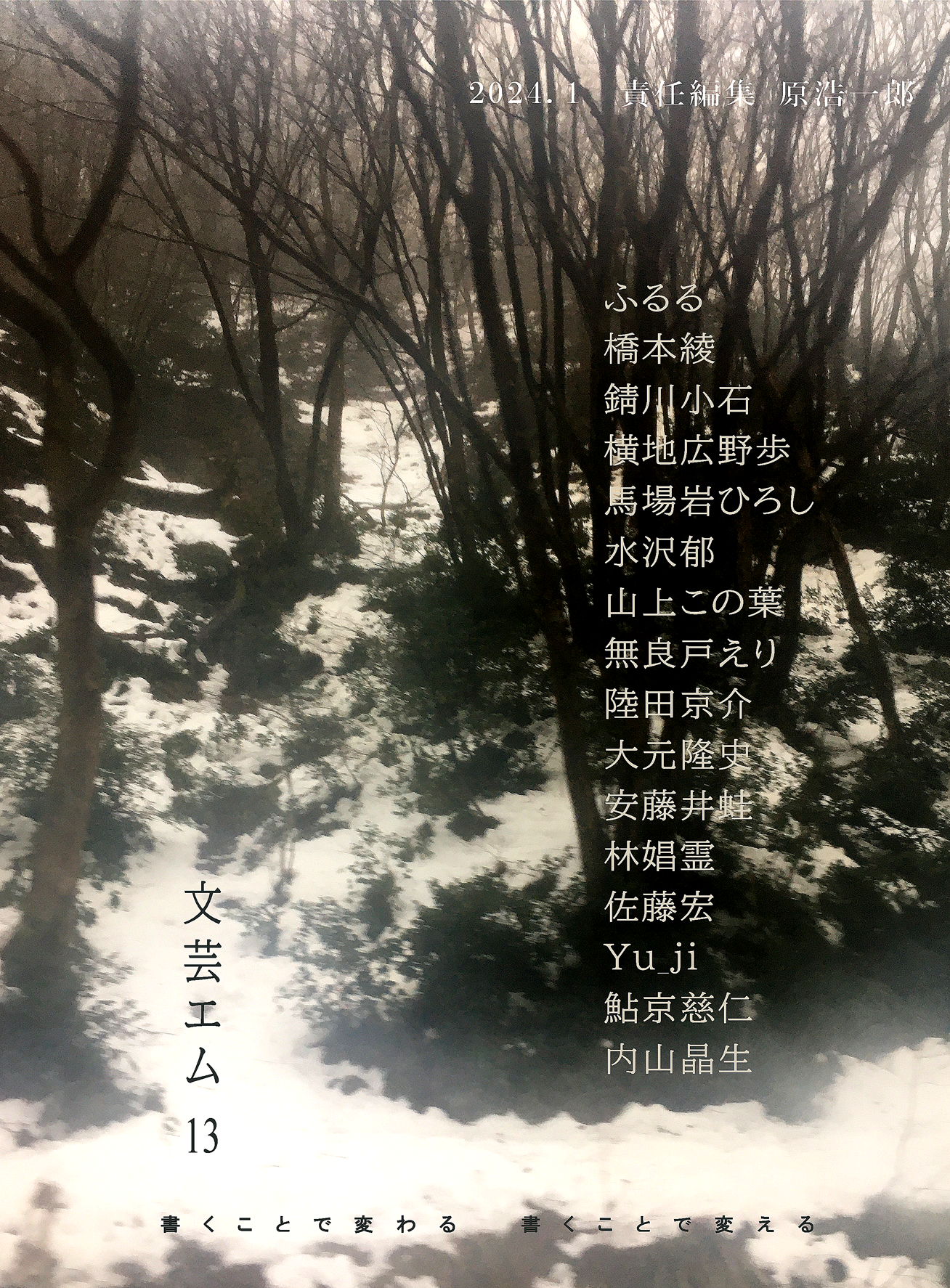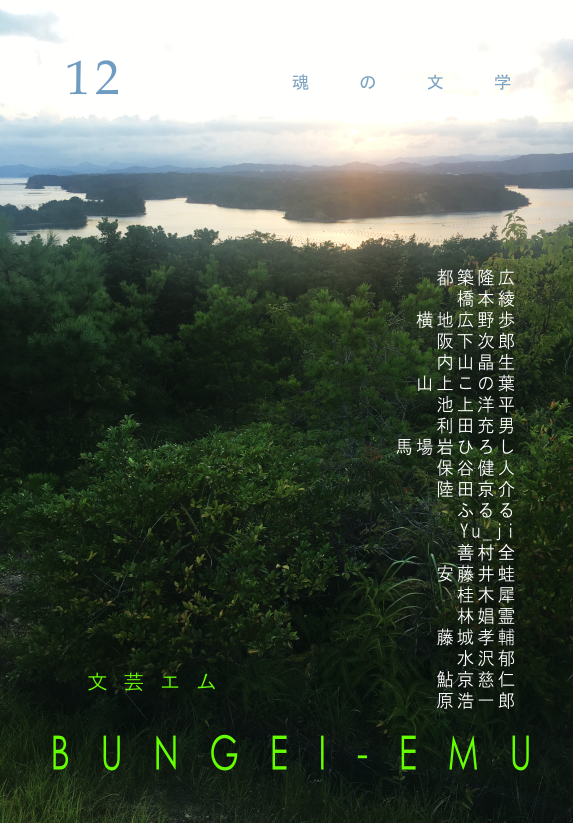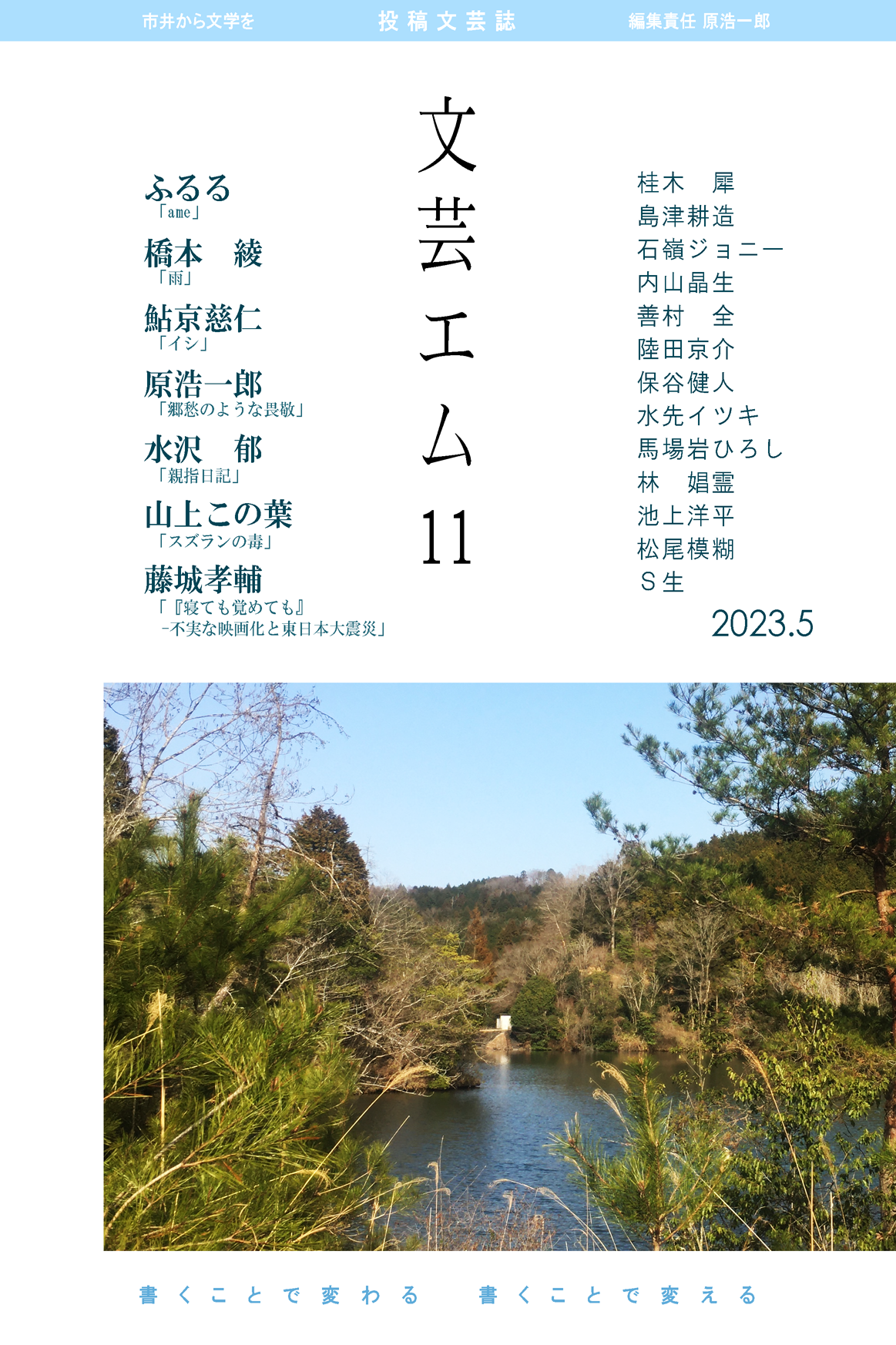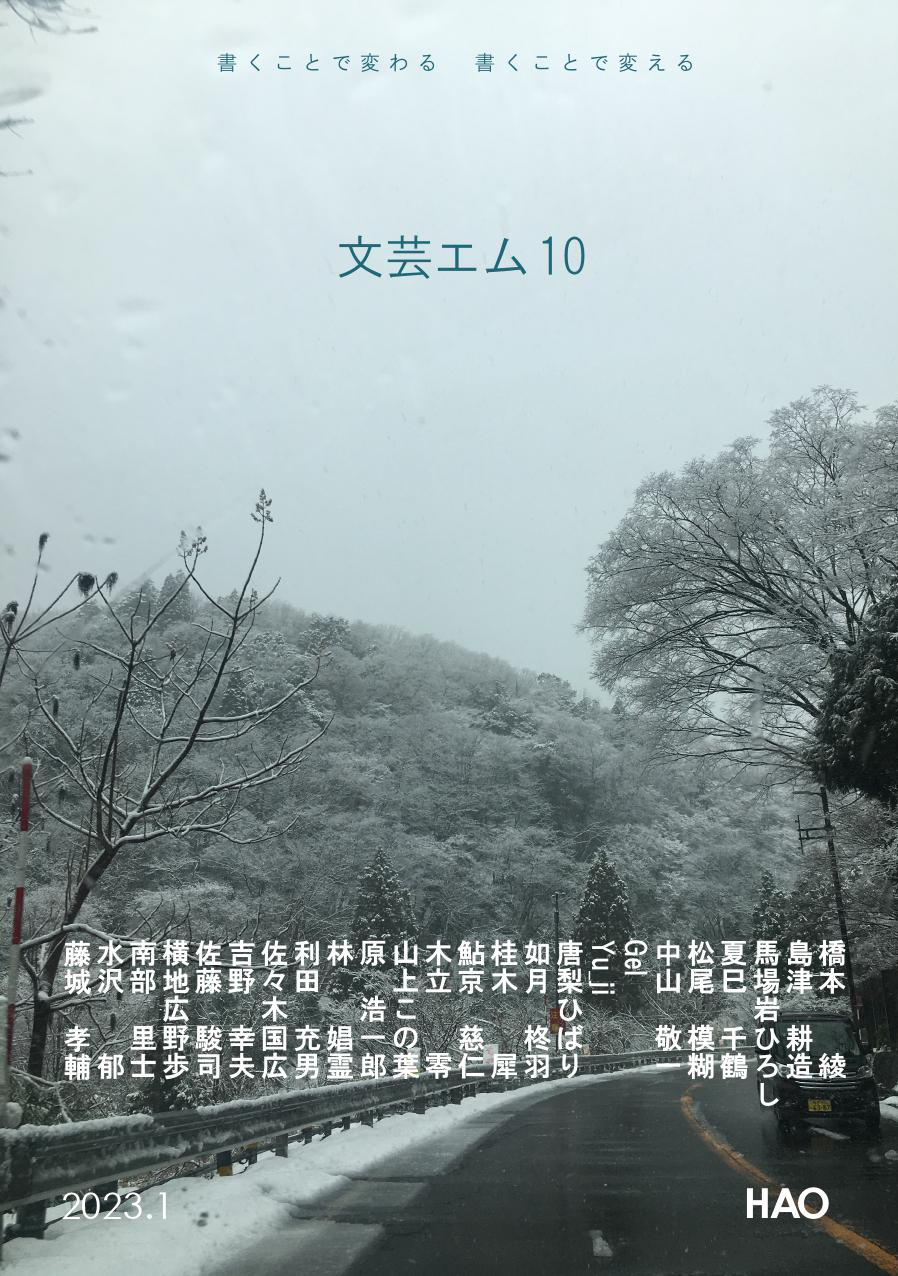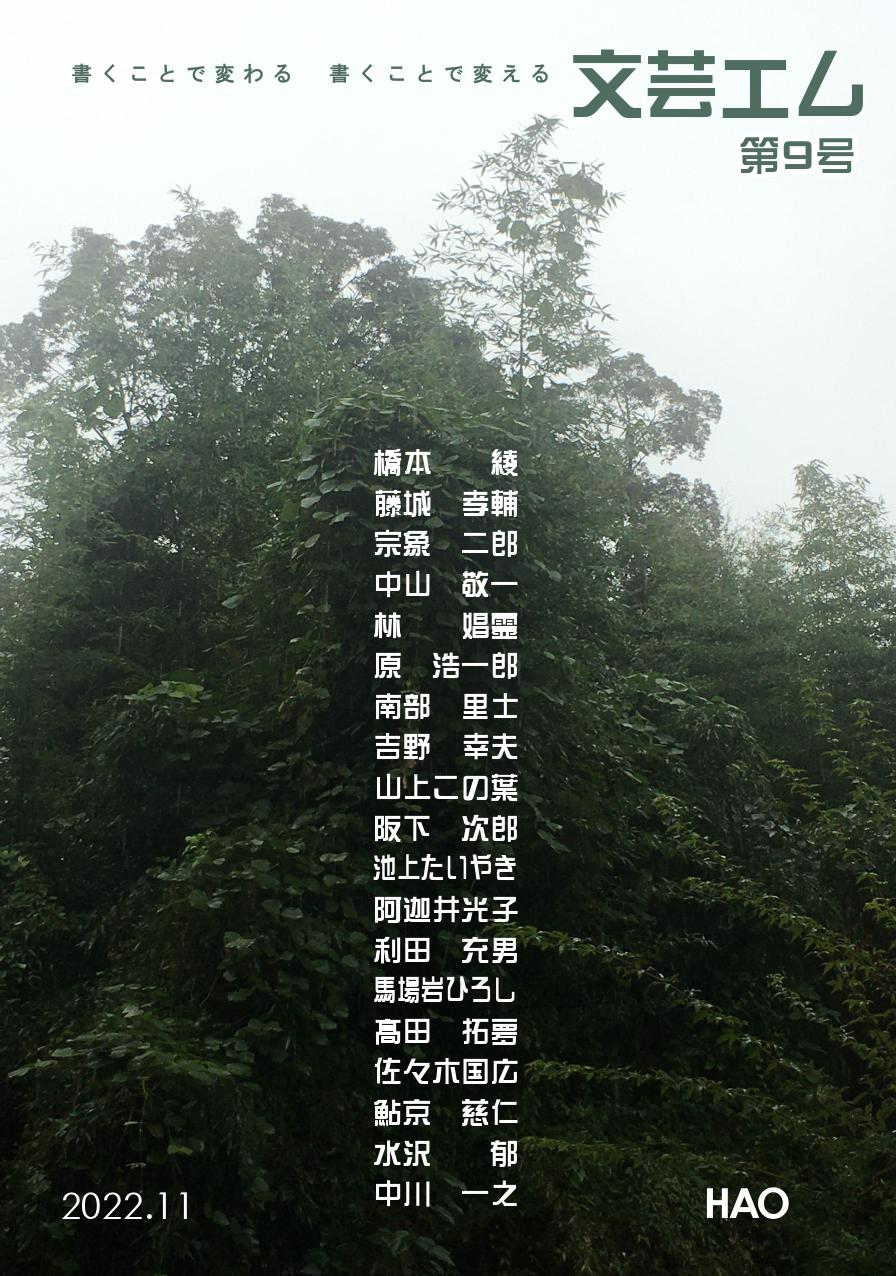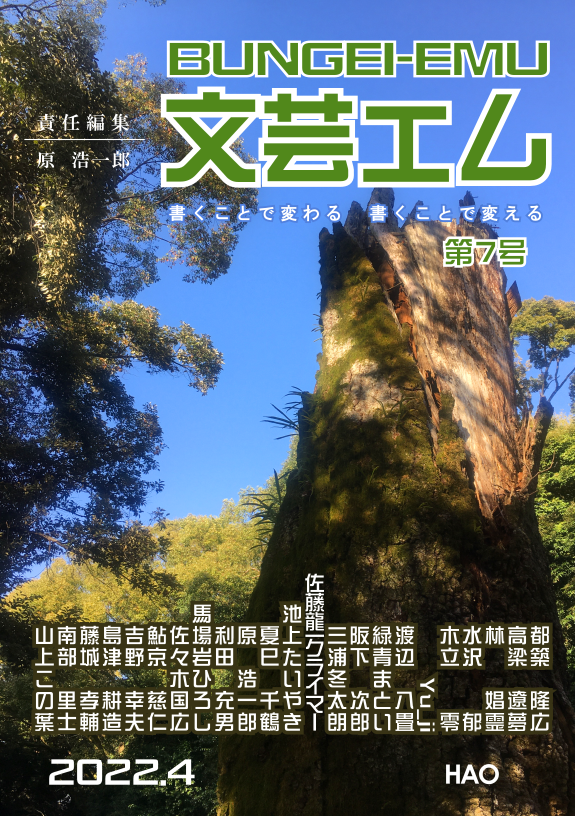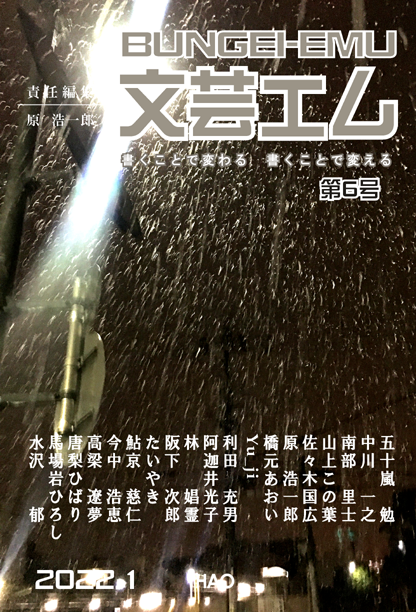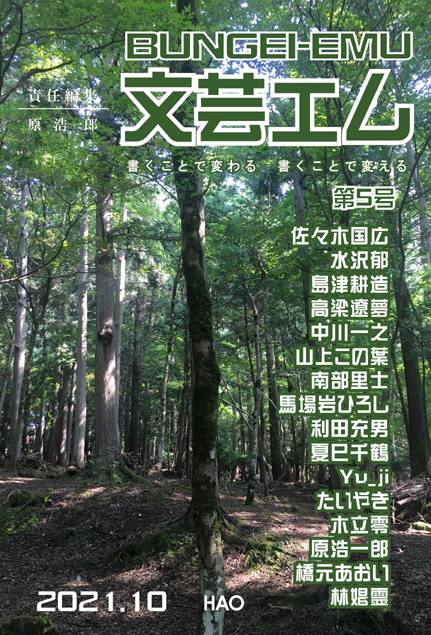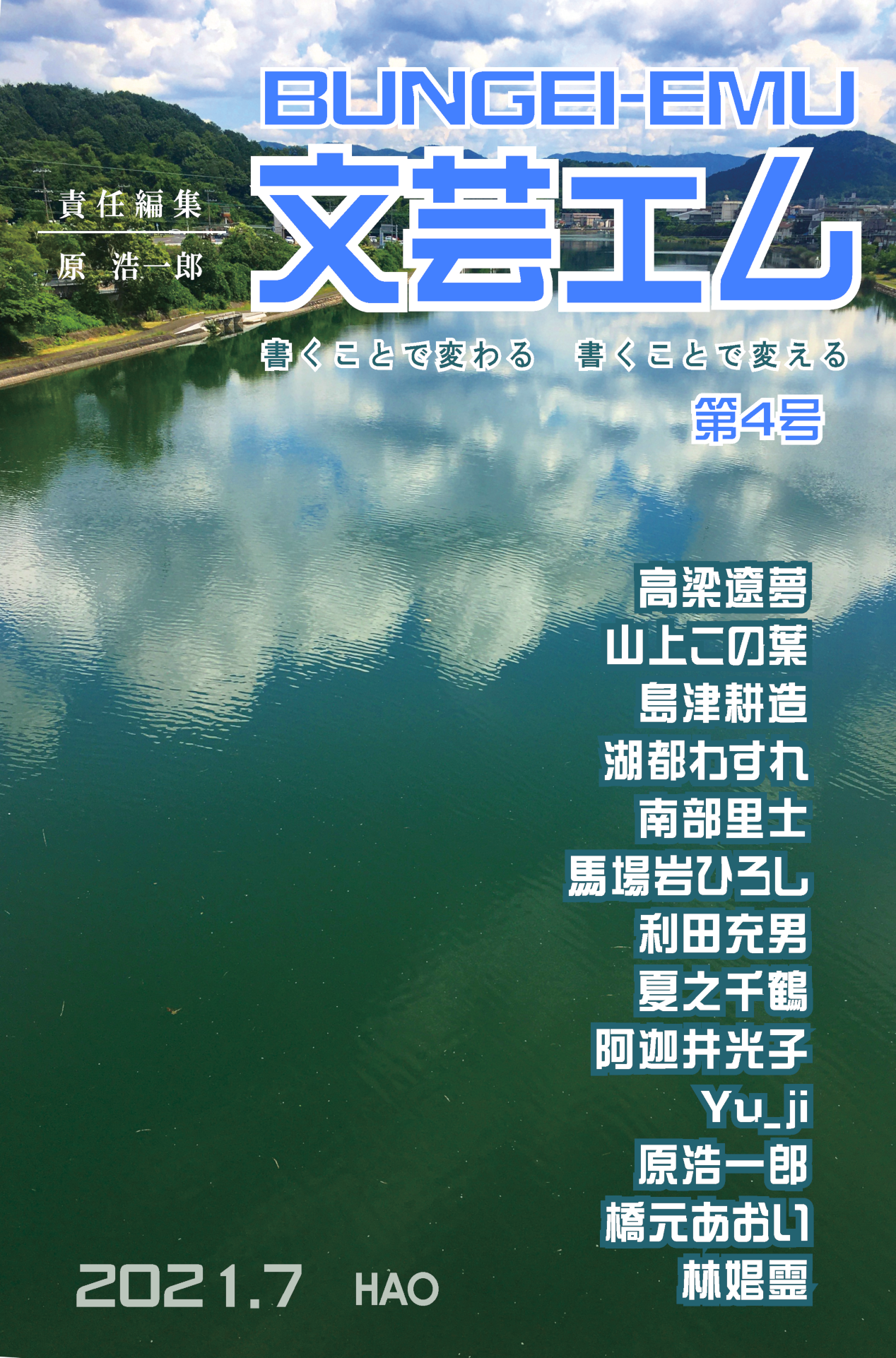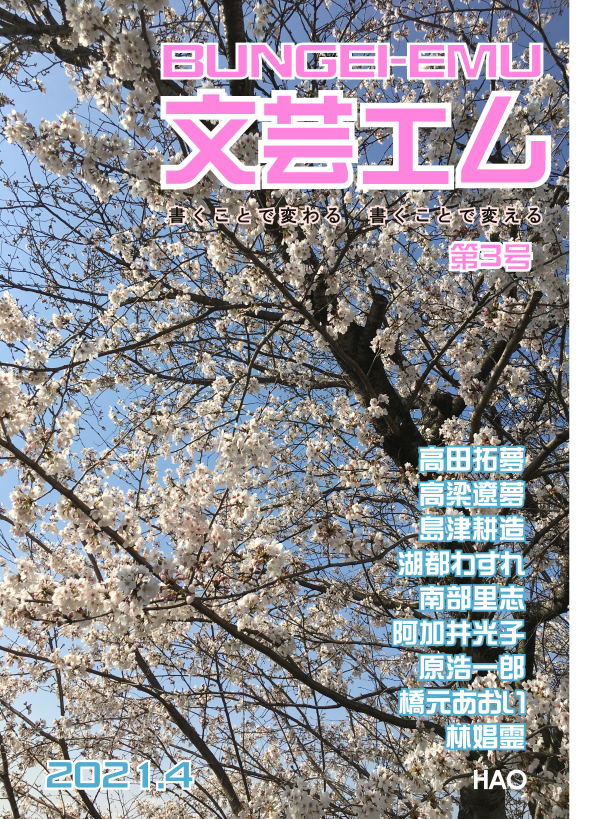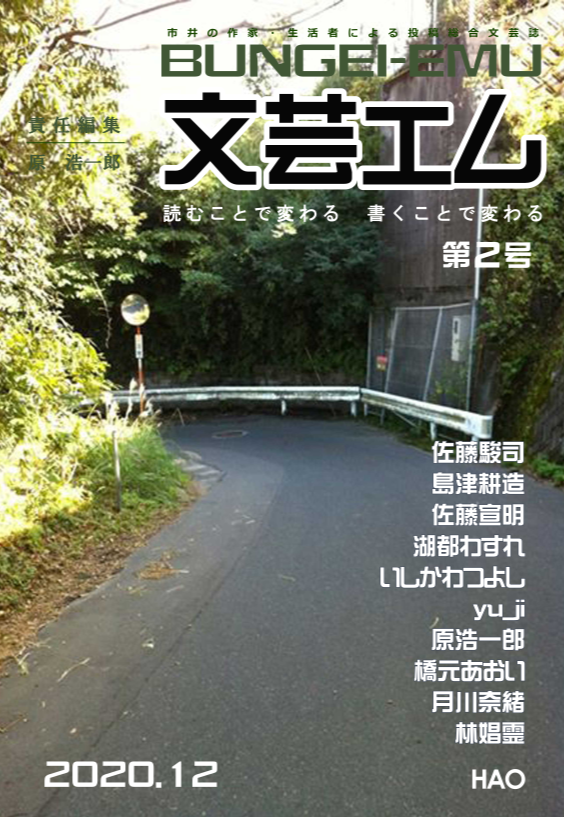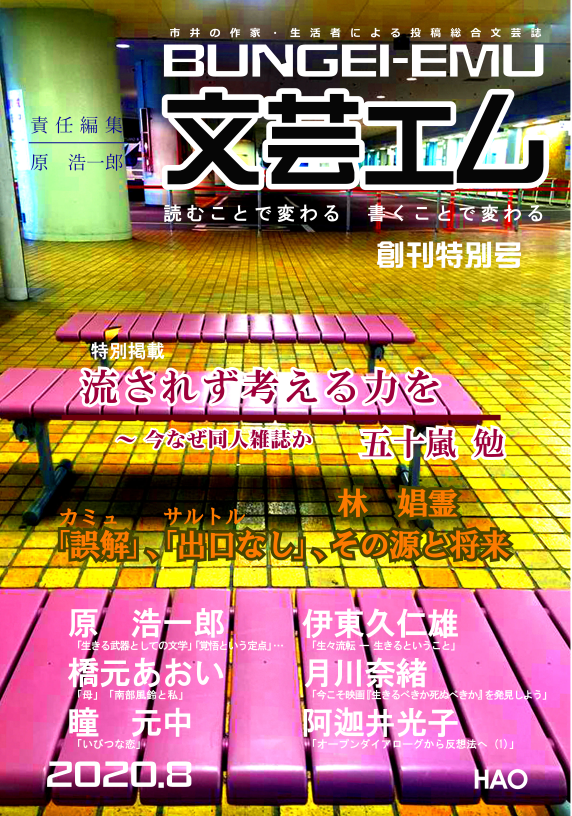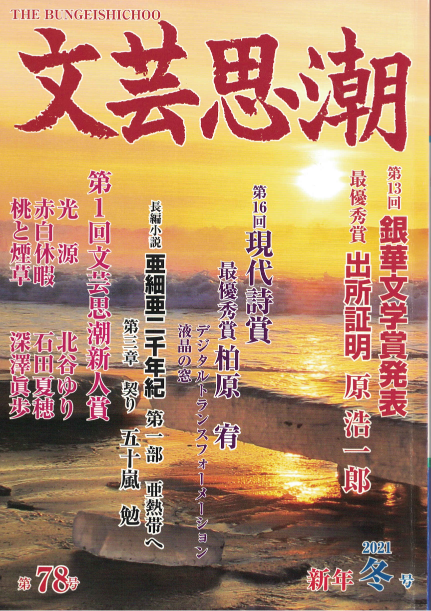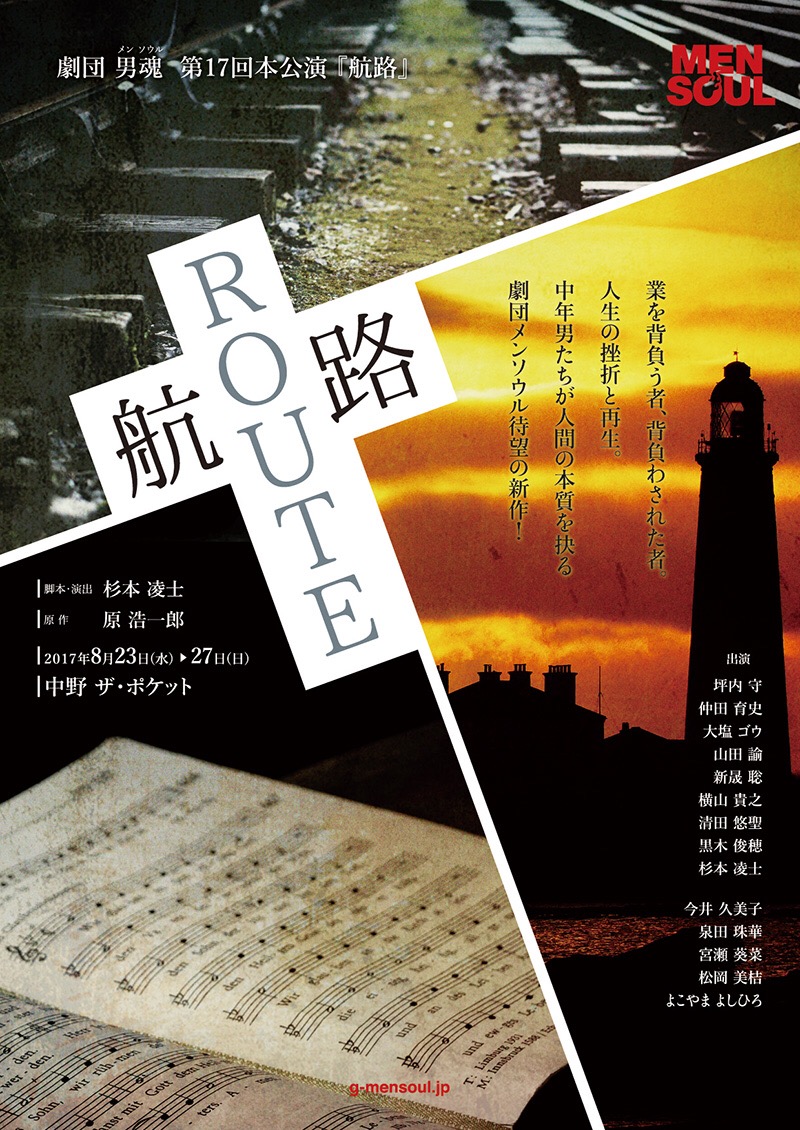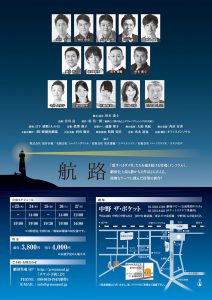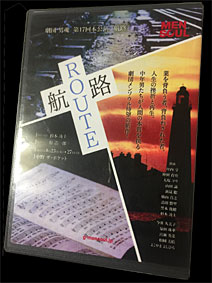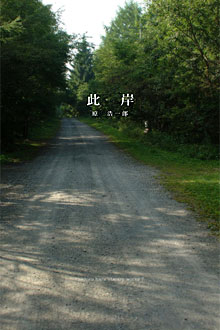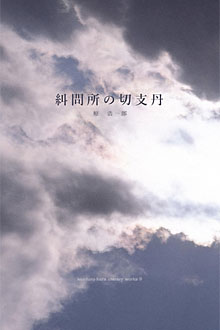どうして達男は殺さねばならなかったのか
―中上健次「火まつり」の「なぜ」
「それがネガティブ・ケイパビリティ、短気に事実や理由を求めることなく、不確かさや、不可解なことや、疑惑ある状態の中に人が留まることが出来る時に見出されるもの」 (J・キーツ 弟宛書簡から)
中上健次による脚本の映画「火まつり」を観た。ラストシーンで主人公達男は、無言で猟銃をかざし、屋敷に集まっていた親族たちを次々に撃つ。さらに自身の二人の男児を射殺したその後に、一人座り込むと銃口を自身の心臓のあたりに当て、その引き金に足の指をかける。響く銃声。しばらく町の日常を映したのち画面はやがて暗転し、途絶するように映画は終幕する。
観ている者は突き放され半ば呆然とする。達男の凶行の理由が、「わからない」からだ。
なぜ達男は殺さねばならなかったのか。居心地の悪い余韻が宙ぶらりんのまま、引っかかって残る。わからない。おかしい。釈然としない問いが消え去らない。なぜ達男は殺したのか。
理由が判然としない。つまりそこに殺人行為があれば、そこにはきっと理由があるはずなのに、それがない。たとえば加害者が抱いていた被害者に対する限度を超えた憎悪や反感、その爆発の導火線となる両者の間ののっぴきならない葛藤など。仮にそれが見当たらないならば、普段からうかがわれた加害者の突発的な暴力性であるとか、了解不能な精神的な異常性、つまり「狂気」を持ち出すこともある。そうして日常に突然立ち現れた不連続なその行為を、どうにかして受け止めようとするものだ。
しかし「火まつり」にはその手掛かりがない。大量殺人に至るその明確な伏線や匂わせがなく、まるで不意打ちを食らったように、あまりに唐突なのだ。
これが中上健次脚本、柳町監督作品でなければ、映画として未熟な失敗作と決めつけられたとしてもおかしくないかもしれない。
しかしである。
そもそも私たちの行為には、〈原因〉があるのだろうか。〈理由〉があるのだろうか。そのように〈説明〉できるものだろうか。また、その説明は単なる「後づけ」でないと果たして言えるだろうか。
「火まつり」は、私たちの理解や納得のありようそのものに、鋭い問いをなげかけているようにも見える。
もうすっかり過去の話になるのだが、私は犯罪を犯した未成年者を「調査」して、その少年らに対する家庭裁判所としての処分を裁判官に具申報告する職務に従事していた。任官前の研修に「非行理解」という科目があった。つまり、当該少年がその犯罪を犯さざるえなかった事情や理由を心理学、社会学、教育学その他人文的知見を駆使して明らかにするというのだ。そこでもっとも重視されるのは少年との一対一の面接である。幼時からの生活歴を丹念に、特にその主観的体験としての側面から振り返り辿ってゆく。30年以上昔の話だから、今やその理念や手法もがらりと更新されてはいるだろう。
当時はカウンセリングや心理セラピーであっても、問題を抱えたクライエント自身が、ときに無意識の深層レベルにさかのぼり洞察を深めることで症状や行動化の所以を自ら覚知することが寛解や本人の利益に資すると信じられていたように思う。専門書や事例集にはその感動的なプロセスがふんだんに紹介されていたはずである。
今それを一切否定しようとは思わないが、たとえば幼児体験に根差すそうした深層心理のメカニズムを「解明」できたとしても、それはすべて、ただの「解釈」に過ぎない。
たしかにバラバラに散乱していた意味のない人生の出来事が、ひとつひとつすべて意味を持って結び合いつながり合い、大きな意味合いが浮かび上がり、「わかる」という「気づき」の鮮烈な体験は救済や悟りといった表現をしたくなるほど人生の前提を再構成する。
それはつまり、答えのない「なぜ」にとどめ置かれている人に、解釈によって「理由(わけ)」が解き明かされ、暗雲ただよう不可解なカオスの荒れ地が、見る間に晴れわたりいきいきと明解に統合されいのちが溢れかえる変貌の瞬間であり、それはまさに待望された「意味」の光臨というべき決定的転回と言っていい。
ことほどさように、もとより人生は渇望する「意味」から疎外され、「なぜ」の荒野に突き放されて歩まれるものなのだ。
そこで「物語」である。
物語とは〈解釈〉のことだ。人を、ものを、ことを語る。そもそも何事かを叙述するとは、すでに情報を取捨して切り取り、或るアングルから描き出すことだ。人が体験し直面している前後無辺の広大で複雑極まりない流動過程の果てない現実など、そのほんの一片を切り取る以外に私たちには扱いようがないのである。つまりまったく太刀打ちできようはずがない現実から背を向け、限定的に組み上げたミニチュアである模造の現実を措定して相手にするしかない。
以前に信仰における比喩として、神意の全体を理解する不可能性を、瀑布から流れ落ちる巨大な瀧水を猪口で受け止めようとするに等しいという喩えを聞いたことがある。
まさに私たちが生きている現実はとめどなく落ちてくる滝であり、その真下で打たれている私たちの手には、いかにも矮小で貧弱な猪口をしか持っていないに等しいのかもしれない。
だから理解の及ばない事態を前にしたとき、「単純化」に飛びつくものだ。それはなにより、輪郭のあいまいな無数の縁起が錯綜し縦横に関係し合う気の遠くなるほど複雑な様相を前にする混乱から解放してくれる。「要するに、これがこうなって、こう」「つまるところ、こういうこと」など、複合や連関を削ぎ落したシンプルな言い換えは魅力的だ。しかし「どのように」という生成過程ではなく、そもそもの「なぜ」を含む単純化には用心したほうがいい。そうした単純化はすでにひとつの狙いのもとに遂行されているものだからだ。その狙いとは事態に対する「意味」の付与だ。
そうした単純化には思想がありメッセージが含まれている。世界は信じられる。努力は報われるべき。人間とはこういうものだ、等々。「こうだから、こうなったのだ」「こうなったのは、こういうわけだ」それは原因となる要素や条件から、おのずと結論が導かれたように見せながら、実は先に思想があり、逆算してその因果を展開していると言った方がいい。それは肯定的なメッセージであれ、逆に世界の不信や敵意を煽る因果を提示する場合であってもだ。いずれにしても、単なる〈解釈〉を〈真相〉と錯覚させる狡猾な罠であることには変わらない。
そして、ここで思想と呼んだ価値のありようなど、普遍性を装いながら時代や民族によって容易にとって代わられるものにすぎない。決めつけや詭弁の扇動や逆張りに翻弄されているにすぎないとも見える。近時もてはやされている「コスパ」「タイパ」「スピード感」などといったスタイルはその格好の隠れ蓑になっているのではないか。
これらはひとえに「答えの得られない〈なぜ〉」に、人はいかに耐え難いかを示してもいる。精神医学界隈でひところ〈ネガティブ・ケイパビリティ〉の概念が注目されたし、湯浅誠はそれ以前から「葛藤をホールドする力」と強調していた。それは「わかる」という答えを性急に求めず、事態をそのままに浴びて分け入ることがますます困難になっている危機の裏返しであるようにも思われる。
だからこそ単純化された虚構の現実である文学世界に人は惹かれてやまないとも言えるし、現実を生きる上で自ら事態を解釈するすべを学習しているのかもしれない。もとより傑出した作家の資質としてキーツはネガティブ・ケイパビリティを見出した。こうした現実と創作世界の二重写しのからくりを、作家であればとうにはなから承知しているものと解すべきなのだろう。
そして「火まつり」に戻る。
中上健次は自ら脚本を書いた映画の公開二年後に、小説として「火まつり」を上梓している。そこにおいて作家は達男の凶行の理由を映画以上になにがしかほのめかし、推測の糸口を「わかりやすく」提示しているだろうか。もし映画表現が作家にとって不足を含んだものであれば、本来の表現フィールドである小説でそれは補われてしかるべきだろうと推測した。果たして、小説「火まつり」に達男の殺人の動機は書かれたか。答えは否である。映画同様に、読後答えのない「なぜ」に突き放された。作家が敢えて「なぜ」に対する答えを、解釈による理解の仕方を、はっきりと拒絶したのだと私は理解した。
「火まつり」は実際に熊野で起こった大量殺人事件に作家がインスパイヤされて書き起こされた。実際の事件においても犯行の動機は不明であったが、心因反応による錯乱と考察する精神科医もあった。中上は注意深く、そうした「精神の異常」に原因を帰結させないよう叙述している。
「その事件は自分がいままで書いて来た小説の顕現化だとも思ったし、私小説で何度も書いた主人公の暴発が成就したものだという思いもつもった」
「岬」の義妹に対する性交、「枯木灘」での義弟に対する殺人、そして「地の果て至上の時」における路地跡への放火などといった、主人公秋幸の暴挙を思わず想起せざる得ないほどに、作家にとって重なり合う衝撃的な事件だったのだ。秋幸に限らない。龍造の縊死も同様だろうし、つまるところ作家自身の異父兄の自死につながるのではないか。
秋幸三部作を大きく父殺しをテーマとする壮大な叙事詩と称する紹介を目にすることがある。それを作家自身が否定しないとしても、やはりそれはひとつの「解釈」にすぎない。決して、解答でないのは明らかだ。一方で中上はそうした単純化された解釈を、内心笑っていたかもしれない。
そして、さらに重なる問いがある。達男はなぜ殺さねばならなかったのか、という以上に事件が同時に突きつけるのは、親戚らは達男に「なぜ殺されねばならなかったのか」という問いだ。
映画「火まつり」では達男が親戚らを散弾銃で殺害する場面は描かれず銃声が繰り返し鳴り響くだけである。そのあとで、達男の構える銃口の先に二人の男児が映る。子どもらは怯えるどころか楽しげに笑い合っている。そして乾いた銃声が響く。
なぜ殺すのか、という問いはそのまま同時に、なぜ殺されるのか、という解答どころか解釈をさえ漆黒の深淵に沈める絶望的な問いを露出させる。自死という殺人の被害者は残された者たちでもあるという。なにより、異父兄の自死によって巨大な虚無の奈落に引きずり落された作家であればこそ、なぜ殺されるのかという凍りつくような絶望の問いを最後に添えずにはおれなかったのではないだろうか。
(文芸エム note から)