「京都TOMORROW」
懐かしい「京都TOMORROW」(1994)が出てきた。
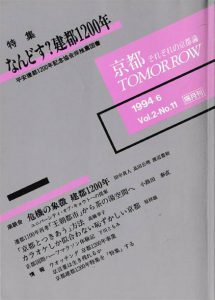
***
カラオケしか似合わない恥ずかしい京都
~ どすえ・舞妓・自社仏閣では唄にならない ~
京都大原三千院、恋に破れた女か一人♪
「女ひとり」(デュークエイセス)
京都の歌と言えば最初に思い出される唄である。「姉三六角蛸錦♪」に似た童歌風の歌い出しは一度聞いたら耳について離れない馴染みやすさがある。しかしその歌詞はというと、もう国宝級の陳腐さである。
これは決して現実を叙情的に描写したものでもなければ、映画のワンシーンですらない。まさしくカラオケのバックグラウンドムービーそのものである。このイメージの貧しさは、複雑微妙で重層的な綾を織り成す現実の世界をひとつの象徴としてのイメージに昇華させることをせず、ただ出来合いの類型的単色イメージをそのままら列してみせただけだからだ。
たとえば、破壊的な憎悪に宿る慈しみの予感であるとか、真っすぐな意志や濁りない誠心に唐突に訪れる倦怠や打算であるとか。或いは自殺するつもりで訪れた町であれこれ土産物を算段しているとか、そういう異質で矛盾するものが交錯し重なり合って織り成している現実の豊かな情景。これを包含し統合するのが象徴としてのイメージである。
ユングは象徴について、これ以上に翻訳が不可能なもっともよくそれをあらわす表現と規定している。一般に誤解されているように、蛇は再生を意味し、銃はペニスを意味するというように単に等号で結ばれる翻訳語、言葉の置き換えでは決してない。そのように表現する以外にその実体を表現できない最高の表現なのである。置き換えは実体のない幻想を架空に作り出す言葉遊戯の道具にすぎない。「恋に破れる」「女」「ひとり」、見事に薄っぺらな架空なイメージを連想させる言葉のら列である。そこにはひとかけらのリアリティもない。「そのままやないか」と言いたくもなるし、「だからなんなんや」とも言いたくなる。すっぽ抜けのわかりやすさだけで、リアルな叙情を喚起させる糸口はどこにもない。
「恋に破れる」。こっけいな勘違いに気づかぬまま思い込みをめぐらせただけだったのか。その夕方電車のホームで投げかけられた言葉と視線からはじまったのか。気軽なホテルの思いがけないベッドではじまったのか。二人仕事をふけて待ち合わせた慌ただしい昼もあったのか。予期せぬ出来事に邪魔されて裸身をさらす機会はいつも先送りになっていたのか。はじめてだったのか。やりなおしだったのか。最後のつもりだったのか。時間と距離が徐々に引き離したのか。すべてを賭けた思いのだけの言葉に冷笑を浴びせられたのか、最後まではぐらかされたのか。すがりつき、恨みまで抱きはしめた男を奇しくも拒絶したのか。一方で新しい男を感じはじめているのか。そういった様々な具象場面にまでのびていくイメージではなく、ここにあるのはそれ以上でもそれ以下でもない「恋に破れる」というただそれだけの架空イメージだけだ。ここには何もない。空っぽな安手のパッケージ。いかにも京都らしいと言えなくもない。
京都は空っぽなパッケージの道具に使うしか、歌の素材としては価値がとぼしいのだろうか。BOROの「大阪で生まれた女」が好きだと東京や宮崎の女が言うのと、大阪の女が言うのとでは、爪楊枝とパトリオットミサイルほどの違いがある。それほど大阪の唄なのだ。京都で歌われてはじめてぐっとくる京都の唄はないのか。
京都にいるときや「しのぶ」と呼ばれたの♪
「昔の名前で出ています」(小林旭)
「あの唄、ほんとうにうまいこと言う。京都でこの仕事ができれば日本中どこでも通用する。それほど、京都のこの業界はきつい。たえしのぶしかない」と、スナックのマスターが言っていたと聞いたことがある。たった一行のフレーズにリアリティが宿っている。よそ者にとっての京都がリアリティにあふれているとは皮肉である。
七〇年代、京都はブルースのメッカだった。西大路から生まれたウェストロードブルースバンド、そして上田正樹とサウストゥーサウス、憂歌団。みな根城は京都のライブハウスだった。L・ホプキンスやJ・L・フッカーに憧れる全国のブルース少年たちが京都をめざした。ブルースだけではない。三条イノダを唄った高田渡、その山科の下宿を唄った加川良、六曜社の前に座り込んでいたシバ、あとトンネルを二つくぐれば京都の町だと唄った友部正人。日々何かが生まれ躍動する息吹がそこにあった。
なのにあなたは京都へ行くの
京都の町はそれほどいいの
この私の愛よりも♪
「なのにあなたは京都へ行くの」(チェリッシュ)
当時名古屋の大学生だった悦ちゃんに泣き顔でそう唄わせたのは、何かの始まりを予感させる強いフェロモンを当時の京都が発していたからだ。決して、「どすえ・舞妓・寺社仏閣」のパッケージ京都ではない。この唄はもう成立しない。


































